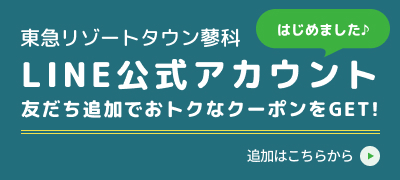こんにちは。タウンセンターの岩下です。今朝9時の気温は-5℃、天候は曇りとなっております。
富士山は、その優美な姿で昔から人々を魅了しています。そして、地元の似た形の山にも「〇〇富士」と名付け、親しんできました。
今回は、信州でみられる”ご当地富士山”をご紹介しましょう。
【高社山】
高社山(標高1,351m)は、中野市・山ノ内町・木島平村の境に位置し、別名「高井富士」と呼ばれています。
30万年~20万年前に活動した成層火山で、溶岩や火砕流、土石流など、多様な地質で構成されています。
ふもとの「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」は、国指定の天然記念物となっています。
【黒姫山】
信濃町の野尻湖西方にそびえる黒姫山(標高2,053m)は、別名「信濃富士」と呼ばれています。妙高戸隠連山国立公園に含まれています。
カルデラを形成する外輪山と中央火口丘(小黒姫山)からなる複式火山で、25万年~4万年前に活動しました。
7万年前には岩屑なだれ堆積物が流下して谷をせき止め、野尻湖ができました。
【富士山】
上田市の鹿教湯温泉の北東には、その名も「富士山」(標高1,029m)(鹿教湯富士)があります。
地質は、新第三紀中新世の内村層(約1500万年前)が分布しており、フォッサマグナの海底に噴出した溶岩や火砕岩から構成されています。
なお、近くには「富士嶽山」(奈良尾富士)があり、麓には「富士山」という地区もあります。
【有明山】
有明山(標高2,268m)は、安曇野市と松川村の境界付近、松本盆地西方の燕岳の手前にある台形の山で、「安曇富士」とも呼ばれています。中部山岳国立公園に含まれています。
地質は、新生代古第三紀の有明花崗岩類(約6000万年前)です。有明花崗岩類は、松本盆地西縁から高瀬川流域、黒部ダムにかけての広い範囲に分布しています。淡いピンク色のカリ長石が特徴で、”桜みかげ”とも呼ばれています。
【蓼科山】
茅野市と立科町の境界に位置する蓼科山(標高2,531m)は「諏訪富士」とも呼ばれ、優美な姿から昔は「女乃神山」と称されました。
数万年前に溶岩円頂丘を形成した火山で、頂部に直径約120m、深さ2mの火口跡があり、るいるいとした岩塊状の溶岩で埋っています。
日本百名山の一つで、八ヶ岳中信高原国定公園に含まれています。
これらの他にも、長野県には、
戸隠富士(高妻山:長野市妙高市)
富士の塔山(長野市)
平尾富士(平尾山:佐久市)
香坂富士(寄石山:佐久市)
会田富士(虚空蔵山:松本市・筑北村)
富士尾山(安曇野市)
木曽富士(卒塔婆山:上松町)
伊那富士(戸倉山:駒ヶ根市・伊那市)
お馬富士(仙丈ヶ岳:伊那市・南アルプス市)
座光寺富士(飯田市)
などなど、”ご当地富士山”がたくさんあります。
近くへお出掛けの際は足を運んでみてはいかがでしょうか。