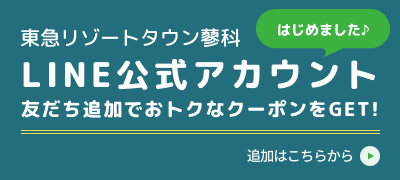こんにちは。本日のブログ担当の岩下です。今朝8時の気温は15℃、天候は晴れとなっております。
江戸時代の三大俳人といえば松尾芭蕉・与謝蕪村・小林一茶ですが、当時から俳諧が盛んだった諏訪地方にも三大俳人の句碑が数多く建てられています。
一覧ページの写真は下諏訪町の水月公園で、三大俳人をはじめ40もの文学碑があります。
【松尾芭蕉】
松尾芭蕉(1644-1694)は、たびたび江戸と西国を行き来していました。その途中で、木曽~甲斐、更科の姨捨山、善光寺など、信州各地も巡っています。
茅野市玉川の多留姫文学自然の里では、茅野市の名勝「多留姫の滝」近くに「かれ枝に鳥の とまりけり 秋の暮れ」という句碑が建てられています。

また、諏訪市金子八幡宮には、「名月や湖水にうかふ七小町」の碑があります。書は諏訪の俳人岩波其残(1815-1894)によるものです。
その他、富士見町の富士見公園や下諏訪町の水月公園など数多くの碑が建立されています。
【与謝蕪村】
与謝蕪村(1716-1784)も全国を旅しており、木曽路や姨捨、戸隠などで句を詠んでいます。
下諏訪町の水月公園には、「不二一つ 埋(うず)みのこして 若葉かな」の句碑があります。
蕪村は俳人でありかつ画家でもありました。碑はありませんが、「名月や うさぎのわたる 諏訪の海」という作品も残しています。諏訪湖の波にうつろう満月の光が目に浮かぶようですね。
【小林一茶】
小林一茶(1763-1828)は現在の長野県信濃町出身の俳人で、信濃国内に俳句を広め一大ブームをつくりました。
旅の途中で中山道下諏訪宿も訪れています。下諏訪駅構内の改札近くには、「甲斐信濃 乙鳥(つばめ)の知らぬ 里もなし」という句碑があります。

また、諏訪大社下社春宮近くの浮島神社には、「一番に乙鳥(つばめ)のくゞる ちのわ哉」の句碑が建てられています。
今回ご紹介した他にも、三大俳人の句碑は諏訪各地にたくさんあります。ただ、芭蕉や一茶の碑は多いのですが、蕪村はあまりありません。流行を反映したものかもしれませんね。
緑の美しい季節、各地の三大俳人の句碑を巡ってみるのはいかがでしょうか。